EMS学長 修了生インタビュー
石井食品株式会社 代表取締役社長執行役員
石井智康氏
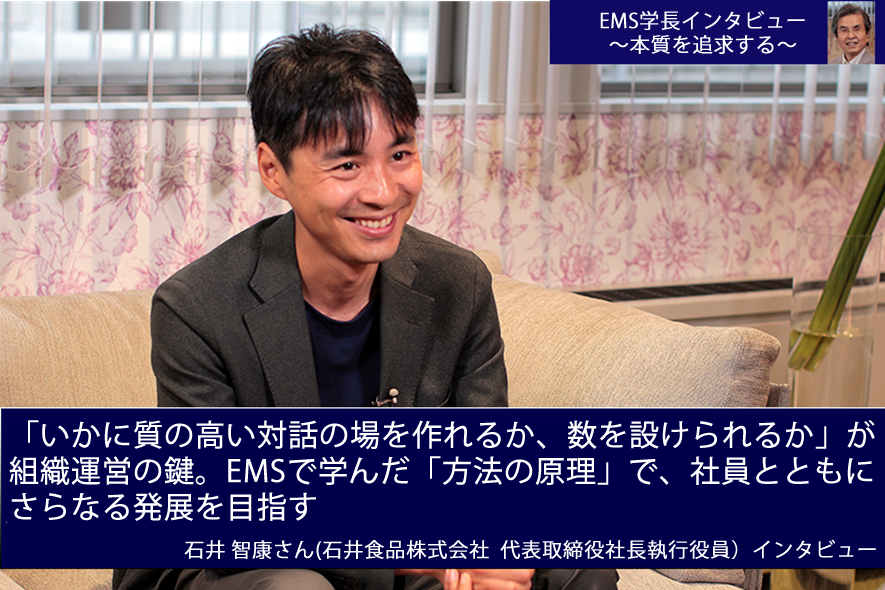
(文・写真・構成:氏家おりえ(EMS0期修了、1期特論Ⅱ受講))
<石井 智康さん プロフィール>
ソフトウェアエンジニアとして、コンサルティング会社にて大企業の基幹システムの構築やデジタルマーケティング支援に従事。2014 年よりフリーランスとして、アジャイル型受託開発を実践し、ベンチャー企業を中心に新規事業のソフトウェア開発及びチームづくりを行う。2017 年から祖父の創立した石井食品株式会社に参画。地域と旬をテーマに農家と連携した食品づくりを進めている。代表取締役社長執行役員として、現在のライフスタイルに合った「豊かな食」のあり方を模索中。認定スクラムプロフェッショナル。アジャイルひよこクラブ幹事。

みなさん、こんにちは。大久保寛司です。
このインタビューでは、私が聞き手になり、「〇〇の本質とは何か」を追求していきます。今回は、石井食品株式会社の代表取締役社長執行役員である石井智康さんをお招きしました。石井さんは、EMS(エッセンシャルマネジメントスクール)の0期生です。石井さんは、なぜEMSに参加され、何を学ばれたのでしょうか。お話を伺います。
創意工夫を続ける
まず初めに、自己紹介をお願いできますか?
石井食品代表取締役社長執行役員の石井と申します。
石井食品の代表的な商品は、無添加調理「イシイのミートボール」や「ハンバーグ」です。皆さんも、量販店などでご覧いただいたことがあるかもしれません。「ミートボール」は1974年に販売開始して、もう40年余りになります。
ロングセラーなんですね
はい。私たちは現在、食品メーカーとして商品を量販店で販売頂いています。もともとは佃煮が発祥の会社です。
商品構成がずいぶん変わったのですね。
そうですね。時代のニーズに合わせて、様々な展開をしています。中華料理や洋食の製造を行ったり、年末におせち料理を製造販売したりしています。玄米パン、中華ソース、サラダなど、かなり幅広く商品を製造している食品会社です。
商品数が、多いんですね。根底にある理念や想いについて、お聞かせ下さい。
私の祖父が、戦後食糧難時代に立ち上げた会社です。食を通じて、どう皆様の健康に寄与するかを大切に考えています。戦後、もののない時代に色々な実験をしながら、体にいいものをどう作って世の中に提供していくかについて、取り組んできました。

常に創意工夫しておられる、と。
はい。その最大の特徴は「無添加調理」です。一般的に、加工食品は食品添加物を使って効率よく美味しい味を実現しているわけですが、私たちは、ここ20年以上、「食品添加物を使わないでどう美味しく作るか」という食品作りにこだわっています。
やってみれば、できる
けっこう難しいんじゃないですか?
これがですね、やってみるとできるんですよ!もちろん創意工夫は必要です。添加物を使った方がよっぽど効率的にはできるんです。けれど、「美味しいものを作る」という原点に立ち返って考えたときに、良い食材を使えばいいですし、一流の料亭は添加物を使わない。きっと、良い食材にシンプルな味付けをするっていうのがよいのではないかと。そこが我々の哲学というか信念としてあります。
「やってみればできる」。これは、やってできた人が言える言葉なんですよね、実は。ただ、できるまでには、ものすごい努力や工夫を含めて、失敗の積み重ねがあって初めてできるわけで。
その信念は、企業風土になっていますか?
そうですね、開発当初は、“すったもんだ”あったみたいですよ(笑)創意工夫しながら実現してきて、今はそれが普通になってきました。「添加物を仕入れよう」っていう動きは会社の中では全く出てきません。
社員は、「自分たちの子どもに胸張って食べさせられる」というのが誇りで、やりがいにつながっているようです。会社として「いいもの作り」をしているのは、社員にもわかっていただけていると思います。
日本一安心安全な食品会社になる
やっぱり「自分の家族に本当に食べさせたい」と思うものを作らないと、食品メーカーに携わる人としては、ちょっと寂しいですもんね。
はい。「美味しい」っていうのはですね、「美味しくて安全」ということだと思っています。ここ30年ずっと、「日本一安心安全な食品会社になる」ということを、目標にしてきたので、社員もそこにはかなり自信があるんじゃないかなと思います。
毎日食しますし、昔のことわざにあるように、「医食同源」で食べること=医療なんだと。だから食べること自身が医の道にかなうのが、本来の食べ方ですよね。
そうですね。私たちのような様々な加工食品メーカーが、戦後の中でどう皆さんに簡単かつ便利に食べて頂くかっていうところの中で貢献してきたと思っています。逆にそれをやり過ぎたが故に「医食同源」というところからは、ちょっとかけ離れてしまうような食生活になってしまったのではないか、というのが今課題になってきているのではないでしょうか。今後、簡便さは担保しつつ、どう「医食同源」「安心安全な食品」という考え方に戻っていくかいうのは、これからの食品産業の大きなチャレンジになるんじゃないかなと思っています。

組織運営っていうのは「人の繋がりと思いをどう作っていくか」
ところで、今世間で大問題になっている事業継承について。なかなか継承できなくて、老舗企業がどんどん消えていくという事態を、国も重要課題として取り上げているんですが、そういう意味では、石井さんが3代目として事業を受け継ぐというのはどんな心境でしたか?
元々、私は継ぎたくないっていう思いが強かったです(笑)ですので、大学卒業後にITエンジニアになりました。
IT業界には、何年ぐらい、いらしたんですか?
約10年です。2017年に石井食品に入社し、2018年6月に代表に就任したんです。
いちエンジニアと、組織をまとめる立場のトップっていうのは別物ですよね。
そうですね。ただ、これまでやってきた「開発チーム作り」には共通点がありました。ソフトウェア業界では、プログラマ一人の力だけではなく、「チームでどうやるか」が一つのムーブメントになっていました。心理的安全性を担保したチーム作りをどう行っていくのかを、組織の中でも、フリーランスという第三者の立場でも行ってきました。本当にそれを実現するには、経営者を巻き込んでやらないとできませんでした。だから、だんだんと経営に近づいていったんです。
なるほど。経営戦略は別ですけど、組織運営っていうのは「人の繋がりと思いをどう作っていくか」ということで、そういう意味では、ITプロジェクトでチーム作りをやるのも経営も、重なっているというお話は、おっしゃる通りだと思いますね。
プロジェクトマネジメントにおける素晴らしいリーダーに共通しているのは、コミュニケーション能力が長けていることですね。これが甘くては、やっぱりリーダーにはなれないんですよね。
はい。チームメンバーからモチベーションをどう引き出してやっていくか、というのはプログラマ以外の仕事も一緒だと思っています。

「目的」を明確にし、やっていることの「見える化」をする
おっしゃる通りですね。プロジェクトのメンバーのモチベーションを高めていくときの鍵っていうのは何だと思いますか?究極は、生産性とか成果をきっちり出すということだと思いますが。
まず、自分たちが何をやっているのかという目的を明確にすること。次に、やっていることの見える化だと思っています。
まず、何のためにやっているか。
そうです。スポーツによく例えるんですが、サッカーだったらボールがゴールに入ることが目的ですよね。見える化も、360度、メンバーがどこで何をしているかわかっている。しかし、仕事だとなぜか、隣にいる人が何をしているのかもわからなかったりします。
本人は、ものすごく頑張って走っているつもりでも、逆走しているかもしれないし(笑)
ですね。また、目的が売り上げかどうかっていうのは、人それぞれの想いも会社の想いも違うので、売上だけじゃないものを設定して、一つのモチベーションとして機能するようにしたいですね。
目的(何のために)を徹底・共有するために、力を入れて何かされたことや意識されたことはありますか?
そこはですね、徹底的に対話する場を作ることです。コミュニケーションの質も大事ですが、量も、かなり大事だと思っています。ですので、コミュニケーションを推進する「場づくり」に力を入れています。だいたい悪いチームは、コミュニケーションがとれていない。目的も不明瞭で、各自がどんな仕事をしているかもわからない。チャットでいっぱい会話しているんですけど、全然実はわかり合ってない。よくあるパターンです。
私が今、捉えた感覚は「いかに質の高い対話の場を作れるか、それから数を設けられるか」。これはもう組織運営の鍵じゃないかと。
まさにそれを、きっちり意識されてやっておられたんだなという印象を持ちました。
一番の学びは、「方法の原理」-ここからが本当のスタート
ところで、エッセンシャルマネジメントスクール(EMS)との出会いは?
大学院に通っていた頃、西條先生の授業を一年間受講していました。その後、SNSなどで先生の活躍は存じ上げていました。2018年の12月に偶然とあるイベントで再会した際に、先生からEMSの話を伺いました。私はちょうど会社の代表に就任して数カ月の頃で、マネジメントとは何かを改めて突きつけられていたので、インプットの場が欲しいなと思いました。何より、天才肌の尖った研究者だった西條先生が、新しい学校を作るというので、ぜひ参加してみたいと思いました。

EMSで、学びや気づきはありましたか?
「方法の原理」ですね。方法の価値・効果は、目的と状況によって変わる、と。
当社のように戦後から73年続いている会社の中で、方法を見失っているものっていうのは、どうしてもたくさんあるんです。
過去のやり方に固まって、そこから出られない。だから元々の「何のために(目的)」というのが徐々に薄まってきて、それをやること自体が目的になっていると。
はい。会社には、いいものもたくさんあるんです。
私の役目としては、変えるべきものは変える、守るべきものは守るっていうところです。シンプルなんですけど、シンプルが故にわかりやすく「方法の原理」っていうところに基づいて、何を変えていくべきかという視点・考え方を授けて頂いたことは、非常に助かっています。
EMSでの一番の学び「方法の原理」が、もう即、仕事場で活かせると。
ただやはり、実践となると難しい。。。
理論だけでしたら、高原で語っているのと同じですからね。現実には、排ガスの世界で生きていかなきゃいけない。その中で実際やっていくっていうのは大変ですよね。
ですので、私としては、これからがスタートだと思っています。EMSで学んだことを、どう自分の中に落とし込んでいくか。寛司さんの言葉も含めて。
私だって、できないです。(笑)
自分で書いた本を読んでいても、誰がこんなのできるんだとか思うこともあります。ただ、「少しでも近づきたいな」と思っています。だから、「私だって、なかなかできないんですよ」と伝えると結構、皆さん、ホッとされるみたいです。70歳になっても発展途上ですよ、というような感じで、学ばせてもらっています。
会社では、工場見学会なども実施しておられますよね?
はい。工場見学会(予約制)があり、試食もできます。また、本社の1階には、子供たちとお母さんが集まれる「コミュニティハウス Viridian(ヴィリジアン)」もご用意しておりますので、ぜひお気軽に遊びにいらしてください。
石井さん、貴重なお話をありがとうございました。
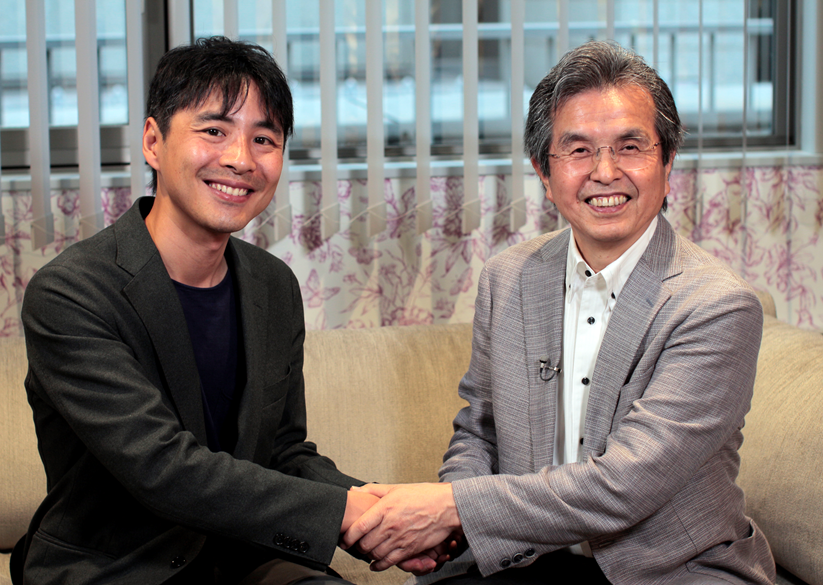
【インタビューを終えて】
石井さんが、これまでのご経験で培った「いかに質の高い対話の場を作れるか、またその数を設けられるか」という点と、EMSで学んだとおっしゃる「方法の原理」の二本柱で、これからも働く方々の幸せと会社の発展に尽力していかれることと思います。
EMSには、経営者の方も多数参加しておられます。ご自身の経営に役立てたい方はもちろん、これからリーダーやマネジャーとしてマネジメントに携わる方々は、ぜひエッセンシャルマネジメントスクール(EMS)にご参加ください。皆様にお会いできることを楽しみにしています。
